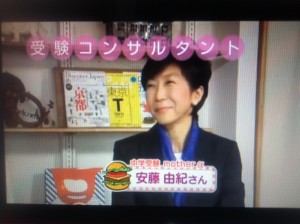中学受験の勉強で塾の復習を子供に任せてはダメなわけ
中学受験の勉強で塾の復習を
子供に任せてはダメなんですか?
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらないときは
「子供の成績が上がらない原因を追求することが重要」
というお話を前回しました。
親子それぞれ
チェック事項がありましたね。
今回は、
「中学受験の勉強で塾の復習を子供に任せではダメなわけ」
についてお話ししていきます。
「中学受験の勉強で塾の復習を子供に任せていること」
を中学受験の勉強をしても子供の成績が上がらない
最も大きな原因として
前回の親のチェック事項であげました。
あなたはいかがでしたか?
中学受験の勉強で塾の復習を子供に任せている
親御さんには耳の痛いお話かも知れません。
中学受験の子供には
「勉強しなさい」と声をかけています。
「勉強しないのは子供の責任」
という親御さんもいらっしゃいます。
しかし、
「中学受験の勉強をしても子供の成績が上がらない」
ことが続いているのであれば
「中学受験の勉強で塾の復習を子供に任せていること」
を変えなければ成績を上げることはできません。
なぜなら、
子供は中学受験の塾の勉強を
何を、いつまでに、どこまでやるのか?は知っていても
「できる様にして」
終わらせることができないからです。
つまり、
多くの小学生の子供は
「中学受験で成績を上げる」
具体的な勉強のやり方を知らないのです。
では
どうすればいいのでしょう?
それは、
「親が関わること」
中学受験の勉強は塾の復習を子供に任せにせず
「勉強に親が関わること」
が重要になります。
では、
中学受験の勉強で塾の復習を子供に任せにせず
親がどのように関わっていくのか?
次々回お話しします。
安藤由紀
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
よろしかったら!
応援クリックお願いします。
↓
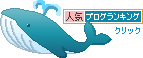
人気ブログランキングへ
![]()
にほんブログ村

読者の皆様に心から感謝です!
タグ
2012年6月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらないときは
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらない・・・
子供が勉強しているのになぜ?
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらないとき
どうすればいいのか・・・
多くの親御さんが悩んでいます。
あなたはいかがですか?
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらないと、
「ちゃんと勉強しなさい!!」
と感情的な言葉がでてしまうこともあるでしょう。
その反面、
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらないと、
「がんばっているのに可哀想」
という気持ちにもなってしまいますね。
お子さんとしても、
中学受験の勉強をがんばっていても
成果が現れないことが長く続けば、
「どうせ勉強しても成績が上がらない」
と、自信をなくしてしまいます。
では、
どうすればいいのでしょう?
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらない
問題を解決させるには
「子供の成績が上がらない原因を追求する」
ことが重要になります。
それでは、
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらない
原因を追及するためのポイントを
チェックしていきましょう。
まず、
はじめに、
中学受験の勉強をしても子供の成績が上がらないときの
親のチェック事項は、ただ1つ。
中学受験の塾の勉強の復習を子供任せにしていないか?
ということです。
中学受験で勉強しても子供の成績が上がらない
最も大きな原因です。
そして、
つぎに、
中学受験の勉強をしても子供の成績が上がらないときの
子供のチェック事項は、勉強の現状について2つ。
1、中学受験の塾の授業と家庭学習で間違えた問題が
放置されていないか?
2、中学受験の塾の勉強の復習を毎週の単元ごとに
できないまま残していないか?
中学受験の勉強をしても子供の成績が上がらないときの
子供の勉強の現状1と2がYESである大半は
子供に勉強を任せていることから起こってます。
より明確に原因を追求するには、
お子さんの勉強の現状をできるだけ詳しく
書き出すことをオススメしています。
中学受験の勉強をしても子供の成績が上がらないときの
家庭学習のチェック事項は、
いかがでしたか?
「中学受験の塾の勉強の復習を子供任せにすること」
については次回お話しします。
安藤 由紀
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
よろしかったら!
応援クリックお願いします。
↓
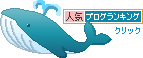
人気ブログランキングへ
![]()
にほんブログ村

読者の皆様に心から感謝です!
タグ
2012年6月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験の勉強で他の子の成績に振り回されていませんか?
中学受験の勉強の成績で
「うわぁ~、
こんなに高得点取るなんてスゴ~イ!」
中学受験の勉強で
あなたは、他のお子さんの成績が気になりますか?
中学受験の勉強をしていると
テストの成績優秀者の点数を見て
焦ってしまう。
また、
「◯◯さんは中学受験の実力テストで
10番に入ったんだって!」
という噂を聞いても
中学受験の勉強に焦ってしまう。
どんな中学受験の勉強をしているの?
どうやってそんなに点数を取るの?
みんなこれ以上、中学受験の勉強をしているの?
うちの子はテストの要領が悪いの?
中学受験の勉強について
テスト結果で焦る気持ちはよくわかりますが
「なぜ?どうして?」
と、他のお子さんの中学受験の勉強や成績に
振り回されてはいけません。
知らないお子さんの中学受験の勉強方法を
いくら詮索してもらちが明きません。
しかし、
いけないと思いながら
他のお子さんの中学受験の勉強の方法や
問題集に目移りしてしまいます。
特に、
中学受験の勉強では
できる子の親御さんの勉強方法を聞けば、
やはり実行したくなってしまいます。
中学受験の同じ参考書や問題集も
影響を受けて買ってしまいます。
それをやれば成績が上がる気がするのでしょう。
お子さんに中学受験の勉強を
「あれもこれも」とやらせてしまいますね。
お子さんからすれば、
中学受験の勉強の問題集を並べられても
見るだけでうんざり。
「勉強のやる気を失う」というのが本音です。
中学受験の勉強をしている大抵のお子さんは
中学受験の塾の復習や宿題で精一杯なのですから
別の問題集までやることは、
なかなかできるものではありません。
これは、
冷静になればわかることですが、
中学受験の勉強では多くの親御さんが
やってしまいがちなことです。
中学受験の勉強をしている子どもは、
能力も学習状況もそれぞれが違います。
他のお子さんと比べてはいけないのです。
中学受験の勉強で親のやるべきことは
他ではなく、
ご自身のお子さんの現状をしっかり把握すること。
そして、【自分の子供にとって】
中学受験の勉強で
今、何が必要か?
そのために何をするのか?
これをしっかり考え的確に行動することです。
中学受験の勉強で
お子さんの成績を上げるためには
「親がぶれずに、やるべきことを毎日続けること」
が重要になります。
心が大きく揺れることもあるかもしれません。
しかし、中学受験に強い気持ちを持って
ゴールに向かって走り続けましょう。
安藤由紀
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
よろしかったら!
応援クリックお願いします。
↓
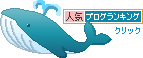
人気ブログランキングへ
![]()
にほんブログ村

読者の皆様に心から感謝です!
タグ
2012年6月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験の勉強で塾の6年生に基礎固めが重要なわけ
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが重要なわけを
あなたはご存知ですか?
中学受験の勉強で志望校の合格を目指す6年生は
「春から夏までの土台作りが最も重要」
というお話しを前回しました。
5年生の塾の復習も
しっかりやるのでしたね。
今回は
「中学受験の勉強で塾の6年生に基礎固めが重要なわけ」
についてお話ししていきます。
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めは、
夏休み終わりまでに終了する様に
塾のカリュキュラムが組まれています。
そのわけは、
中学受験の
「過去問」です。
中学受験の勉強で塾の6年生は
基礎固めを終わらせてから、
自分の志望校の過去問を解くことがベストだからです。
しかし、
中学受験の勉強で塾の6年生が基礎固めを
夏休み終わりまでに終了できない場合もあります。
・中学受験の勉強で塾の6年生の勉強のペースに
ついていけてない
・中学受験の勉強が辛くて勉強に「やる気」がない
・中学受験の勉強で塾の6年生に反抗期
などなど
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが
親の思う様に終わらない理由も様々です。
しかし、
たった1つ断言できることは
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが
夏休み終わりまで終了できないことは
中学受験の過去問を解く上で
「絶対的に不利」だということです。
それでは、
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが
夏休み終わりまで終了しないのが
なぜ絶対的に不利なのか?
私の息子の場合でお話ししましょう。
息子が中学受験の勉強で塾の6年生だったころ、
反抗期と受験のストレスから
基礎固めが終わらないまま秋を迎えてしまいました。
私は、中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが
夏休み終わりまで終了しなくても
「きっと何とかなる!」
と思っていました。
しかし、
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めを終えないまま、
はじめて息子が自分の志望校の過去問を解いて、
その結果に愕然としました。
「中学受験の志望校の過去問が解けない・・・」
「歯が立たない・・・」
反抗期の息子自身も大きなショックを受けました。
中学受験の自分の志望校の過去問から拒否されて、
すっかり自信を失ってしまいました。
もう、春にも夏にも戻れない・・・
自分の志望校の過去問をはじめるまでに
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが終わらないと
「自分の志望校の過去問が解けない現実」を
突きつけられるのです。
その中学受験の勉強の厳しさを
身を持って体験させられました。
いかがでしょうか?
中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが重要なわけ
おわかりいただけましたね。
今は春。
毎日、塾の勉強や中学受験の勉強の基礎固めを
意識を持っておこなえば、
学力がしっかりついていく時期です。
中学受験の勉強が厳しい段階の塾の6年生を、
ぜひ、家族みんなで温かく支えていきましょう。
中学受験の勉強と反抗期については、
また改めてお話ししますね。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年4月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強では、
チャンスを逃してはいけない時期があります。
私立中学の受験で塾の新6年生の家庭学習では
「2ヶ月間我慢して努力を重ねることが重要」
というお話を以前しました。
3つの大きなポイントが
ありましたね。
今回は
「私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は」
についてお話ししていきます。
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強では、
思う様に上がらない子どもの偏差値に
親もイライラしてしまいます。
あなたはいかがですか?
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生、
勉強をやっているのに偏差値が上がらない・・・
偏差値の現状維持すら難しい・・・
しかし、
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強が
どんなに大変でも、偏差値に悩まされても
そろそろ志望校を固める時期がやってきます。
何としても、
一番行きたい私立中学の志望校を受験できる様に
私立中学の志望校の偏差値まで上げていきたい・・・
では、
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は
どうすればいいのでしょう?
それは、
「土台作り」
つまり
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は
「春から夏までの土台作り」
が最も重要です。
それでは、
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強の
「春から夏までの土台作り」
についてお話ししましょう。
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強で
土台作りはどうすればできるのか?
それは、
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の、
夏までの塾のカリキュラムの勉強を
しっかりやることで土台ができあがります。
私立中学の受験の夏までの塾のカリキュラムを
しっかりやるために必要なことは
1、5年生の復習ができていること
2、6年生の勉強の質と量に慣れていること
1は、私立中学の受験で志望校の合格を目指す
6年生の勉強では必須です。
現時点で5年生の復習ができていない部分があれば、
親が単元を絞って勉強しましょう。
2は、私立中学の受験で6年生の勉強で大切な
「しっかり考え理解する勉強」
その上で、勉強を消化するためには欠かせません。
しかし
私立中学の受験で6年生の勉強量が
お子さんの現状にあまりに無理な量であれば、
私立中学の受験の勉強の優先順位を
塾に相談した方がいい場合があります。
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生は、
「夏休みまでが勝負」といえるほど
重要な時期を迎えています。
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の
予想以上の大きな負荷のかかる勉強に
私立中学を受験させるのが
「かわいそう」
と思われるでしょう。
しかし、
私立中学を受験するなら
今、受験の勉強をやらせない方が
「かわいそう」
なのです。
私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は
「春から夏までの土台作り」
が最も重要です。
私立中学の受験、
親子で協力して乗り越えていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年4月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
子どもの勉強の苦手を嫌いにさせない方法
子どもが勉強しているとき
「あっ、“平面図形”後でやってもいいでしょ?」
お子さんは、苦手科目を
いつも後回しにしていませんか?
子どもが勉強している中で
どんな子どもでも苦手科目はあるものです。
子どもが勉強して成績を上げるためには、
苦手意識を克服しなければなりません。
でも・・・
子どもが勉強を何回やってもなかなかできない
一生懸命解いてもわからない
覚えようと思っても覚えられない
よく理解できない
このままでは、
子どもが勉強を嫌いになる日も
そう遠くはなさそうです。
子どもの勉強で
苦手な科目が嫌いになっては一大事。
そのために、
子どもの勉強では
「苦手科目でも、できる意識を持たせること」
が重要となります。
では、その子どもの勉強の方法について
お話ししていきましょう。
子どもの勉強でできる意識を持たせるためには
その科目の苦手意識のないレベルまで
戻る必要があります。
子どもは勉強が、
「苦手だからできない」と思っています。
ならば「できそうなところまで立ち戻る」
ということなのです。
その子どもの勉強の方法は、
やるべき問題の上限レベルを
今、つまずいている問題レベルの
ひとつ下に下げます。
例えば
子どもの勉強の難易度レベルが1・2・3であれば
3の応用までやっていたお子さんは2までに、
2までやっていたお子さんは1の基礎まで下げます。
苦手な科目の子どもの勉強では、
基礎をしっかり説明、理解させたうえで、
簡単な問題から丁寧に解いていきます。
子どもは勉強を苦手と感じているだけに、
苦手科目は頭に入っていきづらい部分もでてきます。
そこは、繰り返してできるようにしましょう。
子どもの勉強で簡単な問題からでも
自分でクリアすれば
「わかる」「できる」
と喜びを感じることができます。
そして、
もうひとつ子どもの勉強で大切なことは
その時に、親が褒めて認めてあげることです。
「よく考えたらできたね!」
「がんばって解いたね!できたね!」
子どもは勉強の中で苦手科目の問題が解けたこと
そのことを親から褒められたこと
この両方から
「できた」と認められた喜びを実感します。
子どもの勉強で「できない」ことは、
苦手意識を高め嫌いになるきっかけとなります。
子どもの勉強で苦手な科目を
好きになることまではできませんが、
子どもの勉強のやり方次第では
普通レベルの問題が「できる」ようになります。
子どもが勉強で
苦手が嫌いにならないためには
「苦手科目でも、できる意識を持たせること」
が重要です。
子どもの勉強では、
親の協力があってこそ
しっかりした土台が出来上がっていきます。
子どもの勉強のバランスをとりながら
親子二人三脚でがんばっていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできること
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできることを
あなたは考えたことがありますか?
中学受験の勉強の家庭学習でやる気が出ない子どもが
勉強するようになるには
「親の言葉の使い方が重要」
というお話を前回しました。
命令的な言い方を替えていくのでしたね。
今回は、中学受験の勉強の「親の言葉」
と合わせて重要なもう一つの親の態度、
「中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできること」
についてお話しします。
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは何だろう・・・
中学受験の勉強の家庭学習は
小学生が一人でこなすのは難しいことです。
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは、
「子どもの勉強に協力すること」
つまり、
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは、
「親が家庭学習にしっかり関わる」
ということです。
中学受験の勉強で家庭学習に
親がしっかり関わることは
中学受験の勉強をする上で大変重要なことです。
それでは、
「中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできること」
について、どのように関わっていくのか?
お話ししていきましょう。
まず、はじめに
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできることは
「中学受験の勉強で家庭学習の予定を立てる」こと。
・中学受験の勉強の家庭学習の
教科、単元、勉強内容と量の確認
・中学受験の勉強の家庭学習の
内容と量に応じての時間配分
これをベースにして、
中学受験の勉強で家庭学習の開始時間からの
予定を決めます。
中学受験の勉強の家庭学習を
私の場合で細かくお話しすると
子どもの帰宅から就寝までのすべての予定時間を
親が紙に書きます。
中学受験の勉強から食事や入浴までも織り込みます。
ここで大切なことは、
中学受験の勉強の家庭学習をはじめる前に
子どもに予定を確認してもらうことです。
そのことで、
家庭学習の勉強を
予定に沿っておこなう意識を持たせます。
中学受験の勉強で家庭学習の予定の紙は
子どもの勉強している机に置きます。
家庭学習の勉強で予定の終わったものには
子ども自身にチェックや棒線を引いてもらいます。
子どもの勉強に対する達成感もでますね。
さて、
中学受験の勉強の家庭学習の準備が整いました。
つぎに、
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできることは
「中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもの隣に座る」こと。
中学受験の勉強の家庭学習で
私はできるだけ隣に座ります。
なぜならば、
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもの
採点・暗記の手伝い・意味がわからない時のヒントなど、
すべてにおいてタイムリーに処理できる
メリットがあるからです。
しかし、
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもの隣に
座れない場合もありますね。
その時は、親が問題で区切って採点するなど、
勉強の進み具合で確認しましょう。
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは、
「親が家庭学習にしっかり関わる」
ということです。
このことは、
しっかり心にとめておいてください。
中学受験の勉強をがんばっているお子さん、
中学受験の勉強をがんばろうとしているお子さん。
親の愛情ある言葉と態度で応援していきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月5日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもには
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもは、
親の思うように勉強をしない・・・
これは中学受験の勉強で
受験生の親の大きな悩みなのではないでしょうか?
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
「勉強しなさい!」と何回いっても
「中学受験の勉強を始めない、はかどらない・・・」
コレはよく耳にしますね。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもが
机に向かっていても、
中学受験のその日の勉強が終わらないこと。
この、中学受験の勉強でやるべき勉強を
消化できない状態は、
中学受験をする受験生の勉強としては大問題です。
中学受験の勉強の家庭学習を
消化できないことが続いてしまえば、
小テスト・復習テストの点数が取れなくなり・・・
必然的に塾の成績が落ちていきます。
それは、もしかすると
あなたの言葉に問題があるのかもしれません。
あなたは、お子さんに「勉強しなさい」と
声をかけていませんか?
中学受験の勉強の家庭学習に
やる気がでない子どもに対して
ついつい言ってしまう命令的な言葉。
「勉強しなさい」
「はやくしなさい」
「ちゃんとやりなさい」
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気がでない子どもに対して親は
勉強時間になると「勉強させなければ」
という意識が高くなります。
そして、
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
強制する命令的な言葉を発してしまうのです。
たとえ、
お子さんが中学受験を決心していても
中学受験の勉強の家庭学習で
命令的な言葉を毎日あびれば、
やる気を失うのも無理はありません。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもは
この「親の言葉」
に問題があることは明白です。
では、この「親の言葉」
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
どういう言い方をすればいいのか?
これからお話ししていきましょう。
まず、
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
「勉強しなさい」の命令的な言い方を
変えることから始めましょう。
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気のでない子どもに対して
「さぁ、勉強しようか!」
「勉強する時間だよ!」
と家庭学習の声かけを変えてみましょう。
子どもは、「親の言葉」をよく聞き、
態度をよく見ています。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
「試してもすぐに変わらない」
と再び命令的な言葉を使うことは、
グッとこらえてくださいね。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
命令的な言い方を連発するようになると
感覚がマヒし、勢いが増していきます。
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気がでない子どもへの命令的な言葉の音は、
不快で家庭内の雰囲気も悪くなります。
気づかぬうちに習慣化している場合が多いので、
自覚して直すよう、心がけましょう。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
親が命令的な言い方を改めれば、
子どもの中学受験の勉強や家庭学習に対する
やる気も戻ってくるでしょう。
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気がでない子ども勉強や時間に関して、
ついつい子どもに使ってしまう命令的な言葉。
親の言葉の影響力が大きいことを
十分理解する必要があります。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもが
勉強するようになるには、
「命令的な言葉を使わないこと」が重要です。
中学受験の勉強の家庭学習の際には
ぜひ、子どもにやる気のでる言葉を
かけてあげましょう!
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方は?
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方は
夏休みでもやっぱり進学塾の勉強が重要?
夏休みは、勉強程々に遊んじゃおうか!?
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方は
そのバランスを悩んでしまいます。
また、
中学受験をする他の進学塾4年生の
夏休みの過ごし方も気になってしまいますね。
そこで今回は、
「中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方」
についてお話ししていきます。
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方は、
大きく3つです。
1、中学受験の進学塾の勉強
2、遊び
3、生活
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方の
勉強については、
以前お話ししている中学受験の進学塾の4年生の目標の
・子どもに知識を定着させること
・子どもに正しい学習習慣をつけること
をベースに考えていきます。
まず、はじめに
1、中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方の
勉強のポイントは4つです。
①毎日決まった時間に進学塾夏期講習の復習
②進学塾の夏期講習の復習を完全に終わらせる
③進学塾の夏休み前までのテストの×問題の解き直し
④中学受験の進学塾の弱点単元の勉強(2単元)
①は、親子で話し合って決めましょう。
②は、中学受験の進学塾夏期講習の休講日を
1区切りと考えて、区切りごとに終わらせます。
夏休みの都合で時間が取れなければ
①・②だけでも大丈夫です。
③、④に関しては中学受験の進学塾通常の
土・日・祝日などで早めにこなせばいいでしょう。
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方の
勉強面はこれで十分です。
つぎは、
2、中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方の
遊びのポイントは3つです。
①夏休みは子どもが好きな遊びを自由にさせる
(できるだけ外遊び)
②夏休みは親子で野山に出かける
(公園でもOK)
③夏休みは親子で博物館・科学館などに出かける
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方の
遊びの
①は、読書・水泳、何でも心を満たす遊びを
笑顔でさせてあげてください。
②は、中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方で
遊びながらの体験学習が狙いです。
中学受験の進学塾では4年生の夏休みしか
チャンスがありません。
このときの持ち物は、
ポケットサイズの植物図鑑と昆虫図鑑。
実物を目にする・触れる・その場で調べる。
これが、一番頭に入ります。
3、中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方の
生活のポイントは2つです。
①家のお手伝いをする
②地球儀・地図・図鑑・辞書を
リビング、TVの側に置いておく
①は、中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方で、
特に台所のお手伝いの体験が理科に有効的です。
例えば、
・お米のとぎ方
・魚の切り身と三枚おろしの違い
・色々な野菜の断面
・カレーライスの材料
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方、
生活は台所で手伝い、お母さんの側で見て学びます。
②は、中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方で
家庭内での親子の会話、TVのニュース・情報番組、
わからないことや興味深いものは
いつでもその場で調べます。
地球儀は、日本との位置関係や時差の感覚を養い、
地図は、更に詳しい情報が得られます。
②は、中学受験の進学塾で
4年生の夏休みの過ごし方だけでなく、
中学受験の進学塾全学年にオススメです。
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方、
いかがでしたか?
4年生の夏休みは勉強だけにこだわらなくていいと
おわかりいただけましたか。
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方は
「やるべき勉強と遊びや体験をたくさん楽しむ」
ことが重要です。
中学受験の進学塾の5年・6年生の夏休みは
遊ぶことが難しくなります。
ぜひ、
中学受験の進学塾で4年生の夏休みの過ごし方は
親子で計画を立てて楽しんでくださいね。
Mother α 安藤由紀
タグ
2011年7月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめたら
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめた・・・
進学塾の復習も“やる気”がなくなってきた・・・
勉強を嫌がり成績も下がってきた・・・
あなたのお子さんは、
このような状態になっていませんか?
中学受験の進学塾で成績が下がってきたら
「原因を見つけることが最も重要」
というお話しを前回しました。
子どもに何が起きているかを知るのでしたね。
今回も引き続き
進学塾の成績が下がることについて
「中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめたら」
をお伝えしていきます。
「中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がっているみたい」
「子どもが進学塾の復習をしっかりやらない」
という親の声を耳にします。
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がることは、
親にとって頭の痛い話ですね。
最近、急に
「中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめた」
と親が感じた場合、
大抵の子どもには勉強に問題が生じています。
中学受験の進学塾で成績が下がる前兆、
もしくは、既に進学塾で成績が下がりはじめているかです。
では、
子どもが嫌がらずに中学受験の勉強をするには
どうしたらいいのでしょうか?
それは、
中学受験の進学塾の勉強で
「子どもの“できない”意識を取り除くこと」
つまり
「進学塾の勉強に自信を持たせること」
が重要です。
それでは
その方法についてお話ししていきましょう。
まず、はじめに
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめた
勉強の原因を調べることからです。
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめた時期の
テストの点数の変化と、できていない内容を調べましょう。
特に単元別に行われる小テストでは、
進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめた時期で
できない単元が割り出せます。
さて、
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめた
単元や勉強のつまずきを親が把握したところで
つぎに、
お子さんと話をしましょう。
中学受験の進学塾の勉強で困っていることや
中学受験の悩みを聞いてみます。
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がる原因が
子どもの言葉からわかるはずです。
「算数の勉強は、嫌い!!」
とお子さんが言ったら算数のその時期の単元が
つまずきのきっかけと考えていいでしょう。
そして、
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がる
教科、単元が明確になれば、
家庭学習の勉強で、親が子どもの隣について
1つ1つ理解させながら丁寧に勉強をやり直していきましょう。
「やってみたらできた」
「よく読めばできる」
と子どもが“できる”自信を持てば、
中学受験の進学塾で子どもが勉強を
嫌がらなくなります。
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がり
成績が下がるきっかけの多くは、
「わからない」「できない」です。
中学受験を成功させるためにも、
子どもが中学受験をする上で深い悩みにならないうちに、
気づいた時点で親が対処しましょう。
中学受験の進学塾で子どもが勉強を嫌がりはじめたら
「進学塾の勉強に自信を持たせること」
が重要です。
中学受験は子どもに大きな負荷がかかります。
子どもの悩みや変化に気づくためにも
親子のコミュニケーションは大切にしていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2011年5月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強