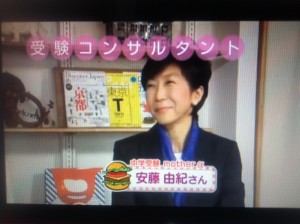中学受験で親が塾の勉強に協力できる環境のつくり方
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
ひとつめのポイント
「子どもの家庭学習のサポート」
について前回お伝えしました。
子どもの学力を定着させることが
大切でしたね。
今回は、
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
ふたつめのポイント
「中学受験で親が塾の勉強に協力できる環境のつくり方」
についてお話ししていきます。
中学受験で親が塾の勉強に協力できる環境といえば
「中学受験の子どもの勉強部屋」
を思い浮かべる親御さんが多いことでしょう。
あなたはいかがですか?
実際に子どもが勉強する場所は、
中学受験で親が塾の勉強に協力できる環境、
勉強に集中するためには大切なことです。
しかし、
今回お話ししたい
中学受験で親が塾の勉強に協力できる環境とは
場所のことではありません。
それは、
「心」
中学受験で親が塾の勉強に協力できる環境で
私が重要視しているのは、
「心の環境」
です。
では、
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
ふたつめのポイント
「子どもが勉強するための心の環境」とは、
どのようなものなのか?
お話ししていきましょう。
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
「子どもが勉強するための心の環境」とは、
中学受験で
「子どもが安心して勉強できる状態」
であることです。
まず、
中学受験で親が塾の勉強に協力して
子どもが安心して勉強するためには、
・親に信頼されている
・親に一個人として認められている
・親がどんな状況でも守ってくれる
・親に愛されている
と、子どもが感じることです。
そのために、
中学受験の親ができることは、
「親が子どもをよく見てあげること、
理解すること」
です。
中学受験で親が子どもをよく見てあげることは、
中学受験の塾の勉強だけではありません。
子どもの生活全般です。
中学受験の塾や勉強、
生活の中で子どもに何かが起きれば、
子どもの言葉や態度が変わります。
親は状況に応じて
様子を見たり、言葉をかけたり
子どもが安心する対応ができます。
また、
中学受験で親が子どもの気持ちを
理解するためには、
中学受験の塾や先生や勉強の話、
楽しいこと苦しいこと、何でも、
子どもの話を聞くことです。
そして、
どんな状況でも共感して
中学受験の子どもの気持ちを
理解してあげましょう。
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
心の環境づくりは
「子どもが安心して勉強できる状態」
にすることです。
最後のひとつのポイントは、
次回お話しします。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年4月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験で親が塾の勉強に協力できること
中学受験で親が塾の勉強に協力できることは、
たくさんあるものです。
「中学受験の勉強で塾の6年生に
基礎固めが重要なわけ」
について前々回お伝えしました。
志望校の過去問までに
終わらせるのでしたね。
今回は、
「中学受験で親が塾の勉強に協力できること」
についてお話ししていきます。
中学受験で親が塾の勉強に協力できることに
どんなことがあるのか・・・
あなたは悩んでいませんか?
中学受験で親が塾の勉強に協力できることを、
悩んでいる親御さんがいらっしゃいます。
はじめての中学受験と中学受験の塾であれば、
中学受験の塾の勉強量とスピードに
戸惑ってしまうのも無理はありません。
中学受験で親が塾の勉強に協力しなくても
塾の復習をしっかりやれる小学4年生は、
ほんの一握り。
ほとんどの小学4年生の場合は、
中学受験で親が塾の勉強に協力しなければ、
うまくいきません。
では、
中学受験で親が塾の勉強に協力できることとは
どんなことなのか?
中学受験で親が塾の勉強に協力する、
そのポイントについて
お話ししていきましょう。
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
ポイントは3つ。
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
ひとつめのポイントは
「子どもの家庭学習のサポート」です。
中学受験で親が塾の勉強に協力できる中で
直接的に成績にかかわる親の協力です。
この
中学受験で親が塾の勉強に協力できる、
家庭学習への協力は大きく
1、 子どものスケジュール
2、 塾の勉強の復習の管理
1の、中学受験の塾の復習を家庭学習でおこなう
スケジュールは、勉強内容を親が把握した上で、
お子さんと確認してください。
2の、中学受験の塾の勉強の復習の管理は、
もちろん、終わることも大切ですが
親が関わり、子どもが勉強の内容を理解しているのか
確認することがもっと大切になります。
中学受験の親も子も、
塾の成績の数字にこだわります。
しかし、
その前に
中学受験の親がこだわるベきところは、
毎日の中学受験の塾の勉強をしっかり復習し、
子どもの学力を定着させることにあります。
中学受験で親が塾の勉強に協力できる
ふたつめのポイントは、
次回お話しします。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年4月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
子どもとの“あいさつ”が大切なわけ
子どもを褒める日常的なこと
あなたは、「あいさつ」を大切にしていますか?
朝、一日の始まりは「おはよう」から。
そして「おやすみなさい」で
一日をしめくくります。
「すべての基本は“あいさつ”から」と
言われるほど、生活する上ではとても大切です。
小さな頃から、そして今でも
子どもは親をお手本に学び続けています。
「あいさつ」は、心を表す言葉。
「褒める」ことを含めて、
親子や人とのコミュニケーションの
きっかけにしていきましょう。
それでは、
毎朝の「おはよう!」から
お子さんがどのような「あいさつ」をしているのか
注意深く観察し、褒めてみましょう。
「あいさつ」がよくできている時は
「いいあいさつね!」
「元気がいいね!」と
褒めてあげるといいですね。
色々な「あいさつ」に応じて、
褒める言葉を工夫してみること。
また、当たり前な「あいさつ」でも、
褒めて、あなたのひと言を添えることで、
お子さんが「あいさつ」する喜びを感じるでしょう。
参考のために、
不器用な私の息子の場合でお話ししていきます。
食事の時「いただきます!」と
元気に言ってくれると
「元気だね!よく噛んで食べてね!」と
声をかけます。
また、「ごちそうさま」と言って
食器をさげてくれると
「ありがとう、助かるわぁ」と、
当たり前かもしれませんが、
私は褒めています。
息子に頼まれた物を渡す時、
大抵「ありがとう」と言ってくれます。
しかし、子どもは「ありがとう」が少し苦手。
ですから、
「“ありがとう”が言えるね!」
と、笑顔で顔を見て褒めます。
時たま、黙って受け取ろうとする時、
私は「はい、どうぞ」と言って渡します。
そうすると「あっ、ありがとう」と気づいて
言うことができます。
これは、優しく何度も繰り返しながら
褒めるよう心がけています。
親が、日常の些細な「あいさつ」を
褒めることによって、
子どもは「自分を、よく見てくれている、
親に認められている」と感じます。
これは、親子のコミュニケーションが
増えるばかりでなく、
子どもの「やる気」がでるという
メリットにもなります。
親子で受験勉強を進める上では
とてもいい状態といえるでしょう。
人の心を開くきっかけとなる
「あいさつ」
人とのコミュニケーションの大切さを
子どもに教えると同時に、私たち親も再認識すること。
そして、いろいろな場面で
子どもの「あいさつ」を褒めていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年4月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
子どもがやる気になる褒め方 ・小テスト
子どもがやる気になる褒め方
これまでの五回で、
子どもを褒めるには
立派な大きなことである必要はない。
むしろ、小さなことで褒められた方が、
子どもは嬉しい。
そして、「小さな褒めること」を
毎日探し続けることで
私たち親自身が
毎日の生活で色々ないいことに
気づけるようになる。
というお話しをしました。
褒めるヒントとして
「時間」「算数の問題」「習い事」
の3テーマを提案してきました。
あなたは、1日1つずつ、
褒めることを探せるようになりましたか?
3テーマの褒めるヒントを元に、
それができていれば、
あなたのお子さんに笑顔と良い変化が現れます。
そして、あなたも
現れた変化に気づくことができましたか?
さて、
「小さな褒めること」を探すことに
だいぶ慣れてきたことでしょう。
今度は
お子さんの日ごろのがんばりからヒントを
差し上げましょう。
「小テスト」をテーマに探してみましょう。
小テストは毎回の授業の復習が
できているかを確認するもの。
点数が取れなければ
「勉強不足」と言ってしまいますね。
お子さんもテストの点数、
そして、何より
点数に対する親からの言葉が気になっています。
そこで、参考のために
私の息子の小テストの点数に対する
褒め方をお伝えします。
息子の塾は、4教科各週1回の授業で、
そのたび小テストが行われます。
「小テストで点数をしっかり取ろうね」と
息子と約束しています。
前回より1点でも上がった場合は、
「よかったね!がんばってるね!」と褒めます。
前回と同じ点数の場合でも
「がんばっているから、同じ点数が取れたね」と
褒めて、がんばりを認めます。
そして、前回より点数が下がった場合でも
「がんばっているよね、問題読み間違えたかな?
一緒に見てみようか」と、
褒めて、がんばりを認めます。
点数が下がった時の息子の反応ですが、
先に、がんばりを認めているので
素直に解き直しに入ります。
そして「あっ、本当だ!問題読み違っていた。」
「漢字、一本足りなかった。あれっ???」
「次は、気をつけようね!」
コレで、丁寧に解く意識を学んで
解き直しも終了です。
小テストで点数が下がったとしても、
お子さんは、いつもがんばっています。
何点取っても
親が、がんばりを認める言葉をかければ
「次回も、がんばろう」
と、やる気がでてきます。
点数だけでなく
お子さんの、よく勉強できているところや
がんばりにも着目して
「小テスト」でも探してみましょう。
お子さんのやる気がでる
「小さなことを、毎日褒めること」
ぜひ、これからも続けていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年4月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
子どもがやる気になる褒め方 ・親の成長
子どもがやる気になる褒め方
これまでの四回で、
子どもを褒めるには
立派な大きなことである必要はない。
むしろ、小さなことで褒められた方が、
子どもは嬉しい。
そして、「小さな褒めること」を
毎日探し続けることで
私たち親自身が
毎日の生活で色々ないいことに
気づけるようになる。
というお話しをしました。
褒めるヒントとして
「時間」「算数の問題」「習い事」
の3テーマを提案してきました。
あなたは、1日1つずつ、
褒めることを探せるようになりましたか?
3テーマの褒めるヒントを元に、
それができていれば、
あなたのお子さんに笑顔と良い変化が現れます。
しかし、あなたにも変化が現れているはずです。
変化が現れていないと感じるとしたら、
それは成長しているのに
気づいていないだけかもしれません。
それは、他人から気づかされることもあります。
私の息子の小学6年の時を例に
お話ししましょう。
息子とは、塾のない日は5時から勉強を始める
約束をしていました。
最近、受験勉強のストレスか
放課後のサッカーで学校を出る時間が遅く、
走って帰宅するも、5時過ぎている状態でした。
そんなある日、私が用事で留守にしていた時のこと、
5時5分前に、私の携帯電話が鳴りました。
自宅に帰宅した息子からです。
息子:「勉強は何から始めればいいの?
その次は何をすればいいの?」
勉強予定を出し忘れた私は、
勉強の順番を話し電話を切りました。
勉強開始時間前に自分から聞いて来るなんて・・・
「初めてだ」どうしたんだろう?
何か意識が変わったのだろうか?
「えらいなぁ~」と感じたので、
帰宅してから真っ先に、そのことを褒めました。
私 :「今日は勉強時間に間に合うように
学校から帰ってきてえらかったね!」
息子:「間に合わないと思って、凄~く走ってきたんだ」
私 :「間に合うように走ってきたんだ!
えらかったね」
息子:「え~っ、いつものママだったら走ってきて
えらいなんて褒めないのに、いつもと違う!!」
私 :「そうかなぁ~」
息子:「いつものママだったら、遅くなって走るんだったら
もっと早く学校を出てくればいいじゃない!っていうよ」
私 :「・・・」
私自身、息子から指摘された
「言い方の違い」に正直、ハッとしました。
驚いたのは、いつもと同じ行動に対して、
私が完全に視点を変えて褒めていることです。
それも、無意識に自然に褒めれている。
息子が感じるほど、私に変化が現れているとは・・・
この日は、自分自身の成長を含めて
親子で「成長」を感じることができた
嬉しい日となりました。
あなたも、
「毎日褒める小さなこと」を探し続けることで、
きっと変わっているはずです。
ただ、それに気付けていないだけです。
親子で成長できる
「小さなことを毎日褒めること」
さらに続けていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年4月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
子どもがやる気になる褒め方 ・習い事
子どもがやる気になる褒め方
これまでの三回で、
子どもを褒めるには
立派な大きなことである必要はない。
むしろ、小さなことで褒められた方が、
子どもは嬉しい。
そして、「小さな褒めること」を
毎日探し続けることで
私たち親自身が
毎日の生活で色々ないいことに
気づけるようになる。
というお話しをしました。
褒めるヒントとして
「時間」「算数の問題」
の2テーマを提案してきました。
あなたは、1日1つずつ、
褒めることを探せるようになりましたか?
2テーマの褒めるヒントを元に、
それができていれば、
あなたのお子さんの笑顔と良い変化と共に、
あなた自身にも良い変化が、
現われてきたのではないでしょうか。
さて、
「小さな褒めること」を探すことに
少し慣れてきたところで
今度は、
少し目先を変えたヒントを差し上げましょう。
「習い事」をテーマに探してみましょう。
中学受験をされるお子さんでも、
小学6年になるまでは「習い事」を
続けていることが多いですね。
スポーツ系の習い事なら、練習風景を見学して。
また、ピアノのような習い事なら、
自宅の練習で成長ぶりや努力の姿が見られますね。
例えば、
・グラウンドを走る姿
・水泳の速さやフォーム
・野球・サッカーのボール裁き
・ピアノ練習曲をスムーズに弾く
など
習い事も種類が多く、
褒めるポイントもたくさんあります。
これは、
上手にできたから褒めるだけでなく、
頑張った小さなことを、何でも褒めることが
できるはずです。
参考のために
テニスを習っていた、
私の息子の褒め方をお伝えします。
テニスのレッスンでは、
まず、軽くランニングをしてから
準備体操をしていました。
息子は喘息でしたが、負けず嫌いで、
何でも1番を意識するタイプです。
ランニングでも、一生懸命な顔をして
必ず先頭を走ります。
いつも私は、先頭を走ることを褒めるのではなく、
一生懸命走る姿勢を褒めます。
レッスンの中では、
「繰り返し何回もサーブの練習をしていたから、
回転のかかったサーブが打てたね」と
上手くできたことも褒めます。
しかし、
コーチのアドバイスを受けて、
自分の悪いところを改善しようとしたり、
届きそうもないボールをあきらめずに追ったり・・・
そのような姿勢を褒めるように心がけていました。
お子さんの努力した姿勢。
少しでも向上したことに視点を当てて
「習い事」でも探してみましょう。
親子の笑顔がふえる
「小さなことを、毎日褒めること」
ぜひ、これからも続けていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきこと
私立中学の受験で塾に入るまでの親のやるべきことで
一生の親子関係にも影響する重要なことがあります。
「私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきこと」
と聞いて
「勉強の習慣」
「漢字の読み書き」
「計算の練習」
など
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことを
一番に「勉強」と考える親御さんが
多くいらっしゃいます。
あなたはいかがですか?
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことで
子どもの「勉強の習慣」も「計算練習」も、
実質、私立中学の受験の塾への準備としては
大切なことです。
しかし、
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことは
親として子どもの勉強の状態を
整えるだけではありません。
というのは、
私立中学の受験で塾に入ってから
私立中学の受験の本番を迎えるまでの塾生活は
小学生には「過酷」。
私立中学の受験の塾の難しい勉強やクラスの昇降。
また、親からの
私立中学の受験の塾の成績へのプレッシャーもあり、
子どもは心を健全に保つことが難しくなるからです。
では、
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき
一番大切なこととは、
どんなことでしょう?
それは、
親であるあなたが
「子どもを理解」すること。
つまり、
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことは、
どのような状況でも
「子どもを把握できるようになること」
が最も重要です。
それでは、
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき
「子どもを把握できるようになること」
についてお話ししましょう。
まず、
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき
「子どもを把握できるようになること」
が、どうしても必要なわけです。
私立中学の受験で塾の難しい勉強をする辛さや、
好きなことや時間の制限。
また、子どもを追い込む結果を招く親の言葉など
子どもには、ストレスがかかります。
この私立中学の受験の塾の影響の
ストレスを蓄積させてしまうと
子どもは心の病にかかってしまい、
私立中学の受験どころではなくなる場合があります。
ですから、
どのような状況でも親は子どもを把握し、
その対処をしなければいけないのです。
つぎに、
その対処方法として
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことは、
「子どもの訴えを逃さず聞くこと」
です。
そして、
私立中学の受験の勉強や塾での辛いことを
「親が認め」
「親が共感」
してあげることが
親のやるべき対処方法となります。
私立中学の受験を親と子で決めること。
私立中学の受験の塾を親と子で選び入塾すること。
そして、
私立中学の受験の本番までの親と子の厳しい塾生活。
どの段階も、大切です。
しかし、
私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき、
どのような状況でも
「子どもを把握できるようになること」
が最も重要です。
私立中学の受験の塾生活での
子どもを把握することや親の接し方は、
私立中学の受験の合否への影響はもちろん、
親と子の一生の関わりに大きく影響するものです。
とても重要なこのテーマは
これからも、随時お伝え続けてまいります。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験を決めるために親がすべきこと
中学受験を親はさせたいのに
子どもが嫌だというときはどうしたらいいの?
中学受験を親がさせたい場合
親にとってちょっとショックな悩みです。
子どもは勉強が嫌いです。
中学受験を親がさせたくても
子どもが中学受験と聞けば
「たくさん勉強しなければいけない」
「好きな習い事も制限される」
「遊ぶ時間も減る」
頭に浮かぶのはデメリットなことばかり・・・
小学3年の子どもが、
あっさり「嫌だ」というのは当然のことです。
逆に、
中学受験を親がさせたい場合は
「大学受験を見すえて中高一貫校がいい」
「6年間充実した学校生活が送れる」
「付属校であれば受験はこの1回でいい」
など
子どもにとってのメリットばかりです。
中学受験で親が考える
「がんばっていい学校に入ることで、
将来の選択肢が増える」
ということも確かです。
中学受験を親が考えるだけで
ワクワクしてきますね。
しかし、
ここで親が忘れてならないことは、
中学受験をするかどうかを決めるのは
「お子さん」だということです。
このことは、
子どもが中学受験をがんばりきるには
たいへん重要なことです。
それでは、
子どもが中学受験を決めるために
親が何をすべきかについて
これからお話ししていきましょう。
まず、はじめに
1、親が子どもの希望を聞きます。
・将来なりたい職業
・将来の夢
・中学校でやってみたいこと
ここで大切なことは、
「お子さんの言葉」で話しをさせることです。
親は、聞くことに徹します。
親の意見や伝えたいことは話し合いの段階で、
押し付けにならない程度にしましょう。
つぎに、
2、親が公立と私立中学校の違いを話します。
中学受験の準備から大学までの流れを
親が話しておく必要もあります。
・中学受験と高校受験のタイミングの違い
・施設や教育環境の違い
・大学受験の対応の違い
・部活動やクラブの違い
お子さんの将来の職業や夢がはっきりしている場合、
学校選択によってその影響が大きいことも
親が話しておきましょう。
参考のため
中学受験の親と子の話について
私の場合をお話ししましょう。
息子が落ち着いている状態のときに
「中学受験のことで少し話を聞きたいんだけど」
と声をかけて話をしました。
まず、1の内容の希望を聞きました。
息子は職業も夢もまだわからない状態でしたが、
・中学で部活をじっくりやりたい
・高校受験は英語があるからイヤだ
この2つを話してくれました。
つぎは、親である私が説明する番です。
公立と私立中学の勉強と環境の違いを話しました。
それから、
小学校から大学までの受験のタイミングと
そのために通塾する期間について、
話をしながら図を書いて説明しました。
公立と私立中学の場合の2パターンを並べて描くと、
あからさまに違いがわかります。
これは、子どもが理解しやすいので
オススメです。
お子さんには十分考える時間をあげて、
考えがまとまったら親と子で話し合いましょう。
子どもが中学受験を決めるためには、
親が子どもの希望を聞き
大学までの流れについて
親が納得のいく説明をすることが重要です。
子どもが進むべき道の決心ができるよう、
私たち親がサポートしていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせるなら
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせたかった
新4年生の2月にできなかったのですが
どうすればいいでしょうか?
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせるのは
いつがいいのか?
あなたも一度は考えた事があると思います。
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせるなら、
多くの塾が中学受験のスタートの
カリュキュラムを組んでいる
新小学4年生の2月がいいでしょう。
しかし、
中学受験で親が子どもの入塾のスタートをさせたくても
できない場合も多くあります。
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
新4年生の2月に希望していても
親の仕事の都合で塾選びができなかったり・・・
上の子どもの受験があったり・・・
中学受験で親が子どもの入塾を希望通りに
スタートさせるのも大変です。
では、
ベストなタイミングで
中学受験で親が子どもの入塾を
スタートさせられなかった場合どうすればいいのか?
お話ししていきましょう。
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせてしまった場合、
大抵の塾の2ヶ月くらいの勉強は、
新しい単元もありますが3年生の復習が中心です。
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせる希望の
4年生の2月を遅れた場合でも、
2ヶ月程度の遅れのスタートなら
大きな負担がかかりません。
つまり、
中学受験で親が子どもの入塾を
遅れてスタートさせるなら
「塾の春期講習や4月くらいまでが負担が軽い」
ということです。
中学受験で親が心配している
遅れて入塾させると負担がかかること。
それは、
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせたことで
先に入塾している子どもより
「勉強」が遅れることにあります。
この
「勉強の遅れ」
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせてしまった場合、
さらにどのような負担がかかるかは
1、中学受験の塾の現在進行中の勉強と合わせて
受けていない授業の勉強の負担
2、中学受験の塾の勉強にみんなから遅れている
という精神的な負担
3、中学受験の塾の生活に皆が慣れてくる頃
塾の生活に慣れていない負担
1では、中学受験で親が子どもの遅れた入塾で
遅れている勉強のフォローをします。
これは、親も子どもも進行している中学受験の塾の
授業と並行しておこなうため負担になります。
2の、中学受験で親が子どもの入塾の遅れの
精神的なフォローをするには、
・親が中学受験の塾の遅れた勉強の穴埋めに協力して
子どもを安心させること
・中学受験の塾の現在進行中の授業の復習小テストで
高い点数をとり自信を持たせること
3は、親も子どもも新しい中学受験の塾生活に
お互いに慣れていく努力が必要です。
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせる
時期には様々な考え方があります。
しかし、
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
新4年生の2月にこだわるのであれば
中学受験で親が子どもの入塾を
遅れてスタートさせても
「中学受験の塾の春期講習や4月くらいまでが
負担が軽い」ということ。
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせてしまったと感じている親御さんは
ぜひ、参考になさってみてください。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験を成功させる親子関係とは
中学受験を成功させたいのに
どうして親のいうことを聞いてくれないのだろう・・・
あなたは、悩んでいませんか?
中学受験で成功するためには、
限られた時間で多くの勉強を
こなさなければいけません。
そのため、
帰宅からその日の勉強に関することまで、
親の協力が不可欠となります。
しかし、親がいくら協力しようとしても、
親のいうことを聞かない。
反抗的な態度で、勉強が前へ進まない。
これでは、中学受験が
上手くいくわけがありません。
では、
どうしたら親子が心を一つにして
合格に向かっていけるのでしょうか?
それは、
「親子の信頼関係を築く」ことです。
これが合格という頂点を目指す土台になります。
親が子どもを信頼し、認めてあげること。
子どもは信頼されることによって、
自分の力を発揮します。
「自分は親に認められている、愛されている」と
感じた時、子どもは安心して親を信頼するのです。
私の場合ですが
志望校を合格した息子とは、
意識せずに信頼関係ができていました。
なぜ、自然と信頼関係ができていたのでしょう?
息子は、5歳から喘息でした。
発作がでれば夜中でも明け方でも病院に・・・
心配はつきませんでした。
ですから、私は息子の様子を
いつも注意深く観察していました。
そのおかげで息子は、
「自分を見てくれている」
「守ってくれている」
「大切にされている」
と感じていたのです。
そして、小さいころから一個人として
あつかっていましたので、
その点でも認められていると感じていたのでしょう。
年末から気管支炎になり心配はしましたが、
親子の信頼関係をしっかり保ちながら
受験日を迎えることができました。
誰もが皆、
入学したい学校の合格を目指して
がんばっています。
受験で合格するために最も重要なのは
「親子の信頼関係を築く」こと。
それがベースとなり、
お子さんは全力で合格に向かえるのです。
さあ、お子さんを信じて
受験日まで応援していきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親