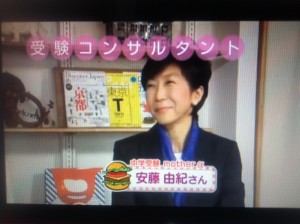中学受験を決めるために親がすべきこと
中学受験を親はさせたいのに
子どもが嫌だというときはどうしたらいいの?
中学受験を親がさせたい場合
親にとってちょっとショックな悩みです。
子どもは勉強が嫌いです。
中学受験を親がさせたくても
子どもが中学受験と聞けば
「たくさん勉強しなければいけない」
「好きな習い事も制限される」
「遊ぶ時間も減る」
頭に浮かぶのはデメリットなことばかり・・・
小学3年の子どもが、
あっさり「嫌だ」というのは当然のことです。
逆に、
中学受験を親がさせたい場合は
「大学受験を見すえて中高一貫校がいい」
「6年間充実した学校生活が送れる」
「付属校であれば受験はこの1回でいい」
など
子どもにとってのメリットばかりです。
中学受験で親が考える
「がんばっていい学校に入ることで、
将来の選択肢が増える」
ということも確かです。
中学受験を親が考えるだけで
ワクワクしてきますね。
しかし、
ここで親が忘れてならないことは、
中学受験をするかどうかを決めるのは
「お子さん」だということです。
このことは、
子どもが中学受験をがんばりきるには
たいへん重要なことです。
それでは、
子どもが中学受験を決めるために
親が何をすべきかについて
これからお話ししていきましょう。
まず、はじめに
1、親が子どもの希望を聞きます。
・将来なりたい職業
・将来の夢
・中学校でやってみたいこと
ここで大切なことは、
「お子さんの言葉」で話しをさせることです。
親は、聞くことに徹します。
親の意見や伝えたいことは話し合いの段階で、
押し付けにならない程度にしましょう。
つぎに、
2、親が公立と私立中学校の違いを話します。
中学受験の準備から大学までの流れを
親が話しておく必要もあります。
・中学受験と高校受験のタイミングの違い
・施設や教育環境の違い
・大学受験の対応の違い
・部活動やクラブの違い
お子さんの将来の職業や夢がはっきりしている場合、
学校選択によってその影響が大きいことも
親が話しておきましょう。
参考のため
中学受験の親と子の話について
私の場合をお話ししましょう。
息子が落ち着いている状態のときに
「中学受験のことで少し話を聞きたいんだけど」
と声をかけて話をしました。
まず、1の内容の希望を聞きました。
息子は職業も夢もまだわからない状態でしたが、
・中学で部活をじっくりやりたい
・高校受験は英語があるからイヤだ
この2つを話してくれました。
つぎは、親である私が説明する番です。
公立と私立中学の勉強と環境の違いを話しました。
それから、
小学校から大学までの受験のタイミングと
そのために通塾する期間について、
話をしながら図を書いて説明しました。
公立と私立中学の場合の2パターンを並べて描くと、
あからさまに違いがわかります。
これは、子どもが理解しやすいので
オススメです。
お子さんには十分考える時間をあげて、
考えがまとまったら親と子で話し合いましょう。
子どもが中学受験を決めるためには、
親が子どもの希望を聞き
大学までの流れについて
親が納得のいく説明をすることが重要です。
子どもが進むべき道の決心ができるよう、
私たち親がサポートしていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせるなら
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせたかった
新4年生の2月にできなかったのですが
どうすればいいでしょうか?
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせるのは
いつがいいのか?
あなたも一度は考えた事があると思います。
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせるなら、
多くの塾が中学受験のスタートの
カリュキュラムを組んでいる
新小学4年生の2月がいいでしょう。
しかし、
中学受験で親が子どもの入塾のスタートをさせたくても
できない場合も多くあります。
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
新4年生の2月に希望していても
親の仕事の都合で塾選びができなかったり・・・
上の子どもの受験があったり・・・
中学受験で親が子どもの入塾を希望通りに
スタートさせるのも大変です。
では、
ベストなタイミングで
中学受験で親が子どもの入塾を
スタートさせられなかった場合どうすればいいのか?
お話ししていきましょう。
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせてしまった場合、
大抵の塾の2ヶ月くらいの勉強は、
新しい単元もありますが3年生の復習が中心です。
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせる希望の
4年生の2月を遅れた場合でも、
2ヶ月程度の遅れのスタートなら
大きな負担がかかりません。
つまり、
中学受験で親が子どもの入塾を
遅れてスタートさせるなら
「塾の春期講習や4月くらいまでが負担が軽い」
ということです。
中学受験で親が心配している
遅れて入塾させると負担がかかること。
それは、
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせたことで
先に入塾している子どもより
「勉強」が遅れることにあります。
この
「勉強の遅れ」
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせてしまった場合、
さらにどのような負担がかかるかは
1、中学受験の塾の現在進行中の勉強と合わせて
受けていない授業の勉強の負担
2、中学受験の塾の勉強にみんなから遅れている
という精神的な負担
3、中学受験の塾の生活に皆が慣れてくる頃
塾の生活に慣れていない負担
1では、中学受験で親が子どもの遅れた入塾で
遅れている勉強のフォローをします。
これは、親も子どもも進行している中学受験の塾の
授業と並行しておこなうため負担になります。
2の、中学受験で親が子どもの入塾の遅れの
精神的なフォローをするには、
・親が中学受験の塾の遅れた勉強の穴埋めに協力して
子どもを安心させること
・中学受験の塾の現在進行中の授業の復習小テストで
高い点数をとり自信を持たせること
3は、親も子どもも新しい中学受験の塾生活に
お互いに慣れていく努力が必要です。
中学受験で親が子どもの入塾をスタートさせる
時期には様々な考え方があります。
しかし、
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
新4年生の2月にこだわるのであれば
中学受験で親が子どもの入塾を
遅れてスタートさせても
「中学受験の塾の春期講習や4月くらいまでが
負担が軽い」ということ。
中学受験で親が子どもの入塾のスタートを
遅れさせてしまったと感じている親御さんは
ぜひ、参考になさってみてください。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験を成功させる親子関係とは
中学受験を成功させたいのに
どうして親のいうことを聞いてくれないのだろう・・・
あなたは、悩んでいませんか?
中学受験で成功するためには、
限られた時間で多くの勉強を
こなさなければいけません。
そのため、
帰宅からその日の勉強に関することまで、
親の協力が不可欠となります。
しかし、親がいくら協力しようとしても、
親のいうことを聞かない。
反抗的な態度で、勉強が前へ進まない。
これでは、中学受験が
上手くいくわけがありません。
では、
どうしたら親子が心を一つにして
合格に向かっていけるのでしょうか?
それは、
「親子の信頼関係を築く」ことです。
これが合格という頂点を目指す土台になります。
親が子どもを信頼し、認めてあげること。
子どもは信頼されることによって、
自分の力を発揮します。
「自分は親に認められている、愛されている」と
感じた時、子どもは安心して親を信頼するのです。
私の場合ですが
志望校を合格した息子とは、
意識せずに信頼関係ができていました。
なぜ、自然と信頼関係ができていたのでしょう?
息子は、5歳から喘息でした。
発作がでれば夜中でも明け方でも病院に・・・
心配はつきませんでした。
ですから、私は息子の様子を
いつも注意深く観察していました。
そのおかげで息子は、
「自分を見てくれている」
「守ってくれている」
「大切にされている」
と感じていたのです。
そして、小さいころから一個人として
あつかっていましたので、
その点でも認められていると感じていたのでしょう。
年末から気管支炎になり心配はしましたが、
親子の信頼関係をしっかり保ちながら
受験日を迎えることができました。
誰もが皆、
入学したい学校の合格を目指して
がんばっています。
受験で合格するために最も重要なのは
「親子の信頼関係を築く」こと。
それがベースとなり、
お子さんは全力で合格に向かえるのです。
さあ、お子さんを信じて
受験日まで応援していきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできること
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできることを
あなたは考えたことがありますか?
中学受験の勉強の家庭学習でやる気が出ない子どもが
勉強するようになるには
「親の言葉の使い方が重要」
というお話を前回しました。
命令的な言い方を替えていくのでしたね。
今回は、中学受験の勉強の「親の言葉」
と合わせて重要なもう一つの親の態度、
「中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできること」
についてお話しします。
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは何だろう・・・
中学受験の勉強の家庭学習は
小学生が一人でこなすのは難しいことです。
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは、
「子どもの勉強に協力すること」
つまり、
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは、
「親が家庭学習にしっかり関わる」
ということです。
中学受験の勉強で家庭学習に
親がしっかり関わることは
中学受験の勉強をする上で大変重要なことです。
それでは、
「中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできること」
について、どのように関わっていくのか?
お話ししていきましょう。
まず、はじめに
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできることは
「中学受験の勉強で家庭学習の予定を立てる」こと。
・中学受験の勉強の家庭学習の
教科、単元、勉強内容と量の確認
・中学受験の勉強の家庭学習の
内容と量に応じての時間配分
これをベースにして、
中学受験の勉強で家庭学習の開始時間からの
予定を決めます。
中学受験の勉強の家庭学習を
私の場合で細かくお話しすると
子どもの帰宅から就寝までのすべての予定時間を
親が紙に書きます。
中学受験の勉強から食事や入浴までも織り込みます。
ここで大切なことは、
中学受験の勉強の家庭学習をはじめる前に
子どもに予定を確認してもらうことです。
そのことで、
家庭学習の勉強を
予定に沿っておこなう意識を持たせます。
中学受験の勉強で家庭学習の予定の紙は
子どもの勉強している机に置きます。
家庭学習の勉強で予定の終わったものには
子ども自身にチェックや棒線を引いてもらいます。
子どもの勉強に対する達成感もでますね。
さて、
中学受験の勉強の家庭学習の準備が整いました。
つぎに、
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもにできることは
「中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもの隣に座る」こと。
中学受験の勉強の家庭学習で
私はできるだけ隣に座ります。
なぜならば、
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもの
採点・暗記の手伝い・意味がわからない時のヒントなど、
すべてにおいてタイムリーに処理できる
メリットがあるからです。
しかし、
中学受験の勉強の家庭学習で親が子どもの隣に
座れない場合もありますね。
その時は、親が問題で区切って採点するなど、
勉強の進み具合で確認しましょう。
中学受験の勉強の家庭学習で
親が子どもにできることは、
「親が家庭学習にしっかり関わる」
ということです。
このことは、
しっかり心にとめておいてください。
中学受験の勉強をがんばっているお子さん、
中学受験の勉強をがんばろうとしているお子さん。
親の愛情ある言葉と態度で応援していきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月5日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもには
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもは、
親の思うように勉強をしない・・・
これは中学受験の勉強で
受験生の親の大きな悩みなのではないでしょうか?
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
「勉強しなさい!」と何回いっても
「中学受験の勉強を始めない、はかどらない・・・」
コレはよく耳にしますね。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもが
机に向かっていても、
中学受験のその日の勉強が終わらないこと。
この、中学受験の勉強でやるべき勉強を
消化できない状態は、
中学受験をする受験生の勉強としては大問題です。
中学受験の勉強の家庭学習を
消化できないことが続いてしまえば、
小テスト・復習テストの点数が取れなくなり・・・
必然的に塾の成績が落ちていきます。
それは、もしかすると
あなたの言葉に問題があるのかもしれません。
あなたは、お子さんに「勉強しなさい」と
声をかけていませんか?
中学受験の勉強の家庭学習に
やる気がでない子どもに対して
ついつい言ってしまう命令的な言葉。
「勉強しなさい」
「はやくしなさい」
「ちゃんとやりなさい」
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気がでない子どもに対して親は
勉強時間になると「勉強させなければ」
という意識が高くなります。
そして、
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
強制する命令的な言葉を発してしまうのです。
たとえ、
お子さんが中学受験を決心していても
中学受験の勉強の家庭学習で
命令的な言葉を毎日あびれば、
やる気を失うのも無理はありません。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもは
この「親の言葉」
に問題があることは明白です。
では、この「親の言葉」
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
どういう言い方をすればいいのか?
これからお話ししていきましょう。
まず、
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
「勉強しなさい」の命令的な言い方を
変えることから始めましょう。
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気のでない子どもに対して
「さぁ、勉強しようか!」
「勉強する時間だよ!」
と家庭学習の声かけを変えてみましょう。
子どもは、「親の言葉」をよく聞き、
態度をよく見ています。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
「試してもすぐに変わらない」
と再び命令的な言葉を使うことは、
グッとこらえてくださいね。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
命令的な言い方を連発するようになると
感覚がマヒし、勢いが増していきます。
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気がでない子どもへの命令的な言葉の音は、
不快で家庭内の雰囲気も悪くなります。
気づかぬうちに習慣化している場合が多いので、
自覚して直すよう、心がけましょう。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもに
親が命令的な言い方を改めれば、
子どもの中学受験の勉強や家庭学習に対する
やる気も戻ってくるでしょう。
中学受験の勉強で家庭学習に
やる気がでない子ども勉強や時間に関して、
ついつい子どもに使ってしまう命令的な言葉。
親の言葉の影響力が大きいことを
十分理解する必要があります。
中学受験の勉強で家庭学習にやる気がでない子どもが
勉強するようになるには、
「命令的な言葉を使わないこと」が重要です。
中学受験の勉強の家庭学習の際には
ぜひ、子どもにやる気のでる言葉を
かけてあげましょう!
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年3月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 勉強
子どもがやる気になる褒め方・親にもいいことが!
子どもがやる気になる褒め方
これまでの二回で、
子どもを褒めるには
立派な大きなことである必要はない。
むしろ、小さなことで褒められた方が、
子どもは嬉しい。
というお話しをしました。
褒めるヒントとして
「時間」「算数の問題」
の2テーマを提案してきました。
あなたは、1日1つずつ、
褒めることを探せるようになりましたか?
2テーマの褒めるヒントを元に、
それができていれば、
あなたのお子さんの笑顔と、良い変化も、
そろそろ現われてきたのではないでしょうか。
そして、あなたにも・・・
あなたは、ご自身の変化に気づいていませんか?
そう、以前にもお話しした通り、
「小さなことを褒める」ことで
親にも大きなメリットがあるのです。
ある日、私はこの変化に気づきました。
このことについてお話しします。
私は「小さなことを毎日褒めるべきだ」と
気づいてから、毎日褒めることを
探し続けています。
この意識をもって子どもに接することにより、
子どもの言葉や態度を、
注意深く観察するようになりました。
その結果、
今までよりもっと子どもの良いところに
気づけるようになったのです。
つまり、
子どもをより深く理解できること。
子育てには
とてもいいことであることは言うまでもありません。
そして、次は
私自身の変化です。
食器を洗いながら、
1日の行動を頭の中で思い出していました。
そういえば、今日
「友人に協力できた事が嬉しかったなぁ」と
思った次の瞬間
「あれっ、私役にたってた?いいことしてた?」と
協力できて嬉しかった後ろにある
小さないいことをした自分に
気づいたのです。
つまり、
子供だけではなく、
今まで気づけなかった自分のいいところに
気づけるようになったのです。
そして、
子供や自分だけでなく
他の人のいいところにも、
自然と気づけるようになりました。
「小さなことを褒める」こと。
そのために毎日褒めることを
探し続けることで、
私たち親自身が
毎日の生活で色々ないいことに
気づけるようになるのです。
親子それぞれにいいことが起こる
「小さなことを毎日褒めること」
ぜひ、これからも続けていきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年2月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
私立中学の受験で志望校や塾の勉強の考えの差
私立中学の受験で志望校や塾の勉強の考えに
ご夫婦でのすれ違いはありませんか?
私立中学の受験で志望校や塾の勉強の考えは、
入塾の時点では細かい話し合いまでは
していないことが多いですね。
私立中学の受験に関しては
志望校や塾の勉強の考えも
しばらくはこのまま進めてもいいでしょう。
しかし、
注意しなければならないのは、
気づかぬうちに
ご夫婦の私立中学の受験の志望校や
塾の勉強の考えがすれ違っていることがあるのです。
私立中学の受験で志望校や塾の勉強の考えで
例えば、
小学5・6年生ともなれば
私立中学の受験の志望校に向けた塾の勉強の量が増え
時間的にも体力的にもキツい状態になります。
私立中学の受験で志望校を目指した
塾の勉強をしている本人も辛いのですが、
それを見ている家族も辛い・・・
ここまで私立中学の受験の志望校を目指した、
塾の勉強が厳しい状態になったとき、
突然父親が
「そんなに私立中学の受験の勉強をしなくても大丈夫」
「塾の勉強は程々でいいんじゃないのか」
と言い出すことがあります。
私立中学の受験で志望校や塾の勉強に対して
父親がこういう考えになると、
私立中学の受験への母親の考えとは
平行線をたどる様になってしまいます。
一番避けたいのは、
私立中学の受験で志望校に向けて
塾の勉強をしている受験生本人に
この言葉を言ってしまうことです。
私立中学の受験の志望校の塾の勉強で、
疲れている辛いときに優しい甘い言葉をかけられれば、
楽な方に流れてしまうのは大人も子どももいっしょです。
一度甘い汁を吸えば、何度も・・・
これで、
一気に私立中学の受験で志望校の合格は
遠のくのです。
私立中学の受験で志望校のレベルを
「どこを目指すのか?」
これが明確になれば
私立中学の受験の塾の勉強を
「どこまでやらせるのか?」
が決まってきます。
そこで私立中学の受験や志望校、
塾の勉強に対する夫婦のすれ違いが起こるのも
また、事実です。
これを避けるためにも、
私立中学の受験で志望校や塾の勉強に対する
ご夫婦の考えを一致させておく必要があります。
まず、
私立中学の受験や志望校、
塾の勉強についての話を定期的におこない、
私立中学の受験や志望校、塾の勉強は
・本人の希望で納得のいく様にさせるのか?
・無理させず手の届く私立中学の受験でいいのか?
など
私立中学の受験や志望校、
塾の勉強についてのご夫婦の考えを
確認しましょう。
もしも、
私立中学の受験や志望校、塾の勉強の考えに
少しでもズレが生じていれば、
話し合いで一致させることが大切です。
また、
私立中学の受験で志望校や塾の勉強をする
お子さんの様子によっては、
私立中学の受験について心がけたいこと等を
確認しておくのもいいですね。
私立中学の受験や志望校、塾の勉強について
「なかなか改まって話しずらい」
という方もいると思います。
そういうときは、塾の保護者会を利用します。
私立中学の受験の塾の保護者会の
内容について簡単な報告をします。
そのついでに、
私立中学の受験や志望校、
塾の勉強に関する考えを確認します。
そうすると、
自然な流れなので私立中学の受験について
かなり話しやすくなるはずです。
私立中学の受験を目指す
お子さんの努力が実るよう
家族が一致協力して応援していきましょう。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年2月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
子どもがやる気になる褒め方 ・算数の問題
子どもを褒めるには
立派な大きなことである必要はない。
むしろ、小さなことで褒められた方が、
子どもは嬉しい。
というお話しを前々回にしました。
そして、小さなことを毎日褒めることを
オススメしましたね。
褒めるヒントとして「時間」で探すことも
提案しました。
あなたは、1週間1日1つずつ、
褒めることを探せましたか?
もしできていれば・・・
あなたのお子さんの笑顔を
見ることができたことと思います。
もしかすると何か良い変化の
兆候が表れているかもしれませんね。
今回は、さらにダメ押し。
もっと効果をあげていただくため、
二つ目のヒントを差し上げましょう。
「算数の問題」をテーマに探してみましょう。
難しく考える必要はありません。
いつもの算数の勉強中
お子さんの隣に座れば、
自然にできることです。
小さなことを、
自然の流れで褒められれば、
それに越したことはありません。
中学受験の勉強で、
算数の内容は難しいです。
その算数の家庭学習の中で、
褒めることを探しましょう。
例えば、
・問題を解く時間が守れたら
・難しい問題が解けたら
・間違い直しが1回でできたら
・式が書けたら
・数字がきれいに書けたら
など
細かいポイントが他にもたくさんあります。
算数の家庭学習のたび、1日1つ褒めましょう。
参考のために
間違えを繰り返す、
私の息子の場合の褒め方をお伝えします。
息子の塾は、算数が週1回の授業で、
復習テストは2種類おこなわれます。
紙の裏表が使われているのですが、
表が計算問題と一行文章題10問、
裏の方が難しい文章題です。
約束していることは、
「表の基礎問題は、間違わないこと!」
それなのに、お約束のように1~2問
間違います。
しかし、息子に一言いう前に
必ず裏の難しい問題の出来具合を見ます。
意外に全部正解していることがあるからです。
まず、裏を褒めます。
「うぁ~、すごいね!裏の問題全問正解、
よくできたね、頑張ったね」
認めてもらった喜びの笑顔がでます。
そして、表のミスに関しては、
「あぁ、裏が全部できていたのに惜しかったね、
次はミスしないようにしようね」というと、
直しは一瞬で終わります。
復習テストに限らず、テストを注意する時は、
まず、全体の出来具合を見てあげてください。
そして、難しい問題が解けていたら、
まず、そのことを褒めてあげてください。
失敗を一番自覚しているのは、本人です。
よくできたところは褒めて、
できなかったところは
「あれっ、計算間違いかな?読み間違った?」
くらいでも大丈夫です。
でも、解き直しは、しっかりお願いしますね!
「小さなことを、毎日褒める」
ぜひ、このまま毎日続けていきましょう。
これを続けると
実は私たち親にも、
とてもいいことが起きます。
これについてはまたの機会に、お話しますね。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年2月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
子どもがやる気になる褒め方 ・時間
お子さんをどうやって褒めていいか
迷っていませんか?
褒められると、大人でも子どもでも
「自分は認められた」と感じます。
そして、嬉しくて自然とやる気が出てきます。
褒めればいいのは分かっている。
でも、何を褒めればいいの?
考えてもわからない・・・
では、あなたは
どうやって褒めるポイントを
見つけていますか?
ポイントは、子どもを褒めるのに、
立派な大きいことである必要はない、
ということ。
小さなことでいいのです。
むしろ、小さなことで褒められた方が、
子どもは、嬉しいのです。
それに気づいたのは、
私の息子が、
同級生のお母さんに
褒められたことを伝えた時です。
「“いつもうちの弟にも優しくてくれるの”って
褒めてたよ!」と伝え
私が「小さい子に優しくできてエライね」と
褒めた時です。
そうしたら、
「えっ、そんな事も見ていてくれたの!」
という感じで
息子の目が、「キラッ」と
嬉しそうに輝きました。
一瞬で気持ちが変わったのがわかりました。
この時、
「小さなことを褒めるってこんなにスゴイ!」
と実感しました。
小さな褒めるポイントは、
意識して探せば気づけるようになります。
小さなことを毎日褒めるべきです。
そこで課題です。
これから1週間
1日1つ必ず褒めるようにしましょう。
なかなか見つからない、
という方もいると思いますので
ヒントを差し上げます。
「時間」で褒めることを探してみるのは
どうでしょうか?
通塾している子ども達にとって
塾のない日の家庭学習はとても大事です。
勉強する教科・休憩・食事などを
「時間」でしっかり区切ります。
例えば、
・友達と遊んできた帰宅時間
・食事や休憩の終了時間
など
時間の節目をポイントに考えてみてください。
1日1つの目標は達成できそうですね。
参考のために、
時間をなかなか守れない
息子の場合の褒め方をお伝えしておきます。
息子の勉強スタート予定時間は、pm5:00~です。
いつも、pm5:30~の30分遅れになっていました。
注意はするのですが・・・
それがある日、自分でpm5:15~始めたのです。
チャンスです!
「あれっ、15分しか遅れてないね~
今日はエライね!頑張ったね!」
それから、勉強スタート時間が
ドンドンpm5;00に近づいていきました。
タイミングを逃さないことが、
いい結果につながることが多いのです。
お子さんを、どうやって褒めていいか?
もう迷いませんね!
「小さなことを、毎日褒める」
いい親子関係を築く上でも
とても大切なことです。
ぜひ、
この小さな一歩を始めてください。
大きな成果の違いが出るはずです。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年2月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 親
中学受験の塾の入塾を決める“あること”
中学受験の塾に入塾すること
お子さんに中学受験をさせることに
迷いはありませんか?
中学受験の塾に入塾することも
中学受験も小学生にとっては過酷です。
中学受験の塾に入塾すれば、
勉強量も多く時間に制約された日々・・・
常に成績・テストの順位と厳しい戦いを続けて
中学受験の塾では受験の準備をしていきます。
中学受験の塾の入塾で多いのが、新小学4年生。
入塾する多くのご家庭では、小学3年生で
中学受験を決断することになります。
もちろん私も例外ではありません。
小学3年生で決断した
「中学受験と塾の入塾について」
私の長男の場合でお話ししていきます。
長男は新小学4年生の2月、
二男は3年後の3月に中学受験の塾に
入塾しました。
長男は、小学3年生でしたが
私の中学受験の話から
自分でメリットをみいだし、
自分で中学受験と入塾を決めました。
私は「本人が中学受験したいならそれでいい」と・・・
しかし、長男は喘息もちでしたので、
過酷な中学受験と塾生活に対して、
不安もありました。
「リスクを背負っての中学受験、
中学受験に向いている子どもだろうか?」
そこで私は「あること」を行い
中学受験や塾の入塾が大丈夫なのか?
その反応や様子を見ることにしたのです。
その中学受験や塾の入塾の適性をみる
「あること」とは!
「テスト」です。
中学受験の塾でおこなわれる
2万人規模のテストを受けさせました。
中学受験の塾でおこなわれる
テストの経験も初めて。
順位や偏差値も参考になります。
しかし、私が注目していたのは
中学受験の塾でおこなわれる
テストの「結果」ではありません。
中学受験の塾のテスト返却時の反応です。
つまり、
中学受験の塾でおこなわれるテストの
「長男の点数や順位に対する
こだわりのレベル」です。
長男は、中学受験の塾のテスト結果が
待ちどうしかった様です。
「何点だろう?何番だろう?」と・・・
中学受験の塾のテストの
自分の頑張ったことに対する
「結果」に、こだわっていました。
この中学受験の塾のテストの
息子の様子を見て、
「中学受験への迷い」が消えました。
「過酷でも中学受験をさせてみよう!
中学受験の塾に入塾させてみよう」
親がサポートしていこうと決断しました。
そして、
親子で入塾を希望して候補に挙げていた
中学受験の塾も、
この様子を参考に入塾させる決心がつきました。
子どもの性格や家庭環境も様々です。
中学受験の塾の条件や状況によって、
また、実際入塾することによって
子どもは知らない一面を見せることもあります。
親は、わが子の性格や勉強への反応を
十分知っておく必要があります。
中学受験や塾の入塾を迷われている場合は、
塾などの「テスト」を受けて、
中学受験や入塾へのお子さんのタイプや
適性を見てみるのも、一つの方法です。
中学受験の塾のタイプや入塾の考え方は、
お子さんやご家庭によって違いがあります。
中学受験の塾の入塾に関しては、
ぜひ、ご自身で確認して納得のいく決断を
してくださいね。
Mother α 安藤由紀
タグ
2012年2月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:中学受験 塾